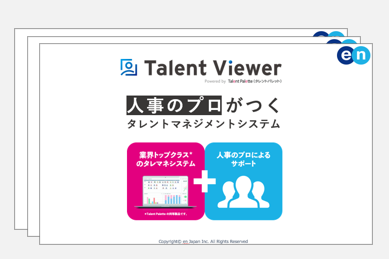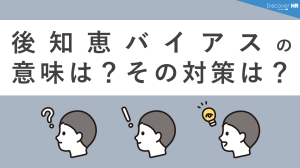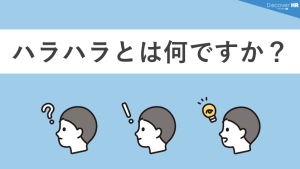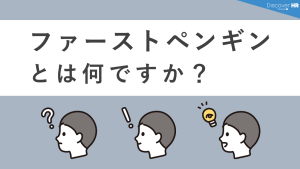確証バイアスの意味は?その対策は?
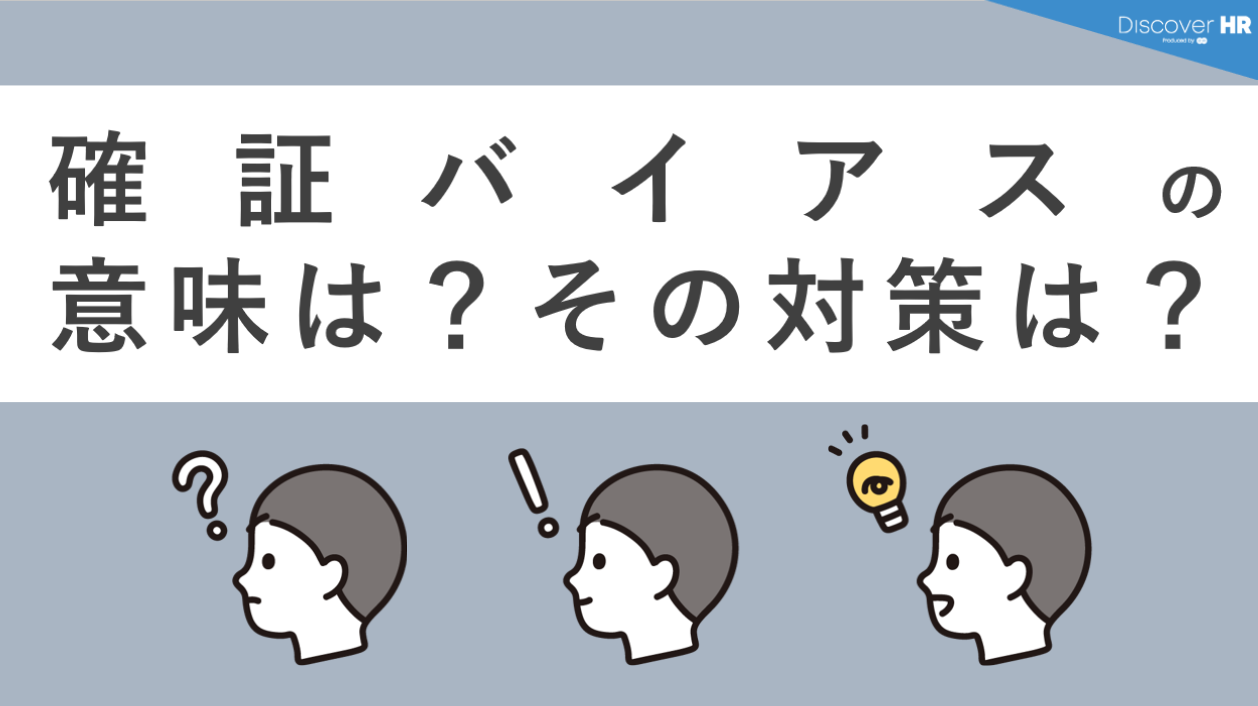
A:確証バイアスとは、人が思い込みから生じた仮説を検証するために、自分にとって都合の良い情報ばかりを集めてしまう傾向のことです。ビジネスシーンの他、日常生活においても確証バイアスはよく見られます。
確証バイアスの分かりやすい例を挙げましょう。
血液型の例
日本では血液型による性格判断が比較的有名です。A型は几帳面、B型はマイペース、O型はおっとり、AB型はちょっと変わり者。こんなパターン分けを誰でも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
実は科学的根拠も足りないという見方もある血液型による性格判断ですが、どうして「当たっている」と感じてしまうのでしょうか。
これも、確証バイアスの代表的な例だと考えられます。
例えばA型の人が掃除をしていると「やっぱりA型はマメだな」と感心したり、B型が遅刻をしてしまうと「これだからB型は・・・」と指摘されたりします。
ここで、A型の「掃除をする前は机が散らかっていた事実」や、B型が「いつもは5分前には到着している事実」があったとしても、見過ごされてしまっているのです。
人事領域における確証バイアス
人事のお仕事をする上でも、確証バイアスは起こります。
よくある例を考えてみましょう。
〇〇大学出身は優秀?
今でこそ、学歴重視で採用することは古いとされていますが、こちらも確証バイアスが起こりやすい事例の1つです。
たまたま○○大学の学生が多く採用されたのち、入社後に数名続けて目覚ましい成果を上げたとします。
「もしかして○○大学出身は、当社で活躍する傾向にあるのかな?」
そう感じてしまうと、以降○○大学出身者が活躍するたびに、「やっぱり〇〇大学の学生は当社と合うんだ!」と考えてしまいます。実は他の大学より採用数が多かったという事実に目が向きにくくなってしまうのです。
確証バイアスを防ぐ対策は?
確証バイアスを軽減させるためには、「反証する情報」を取り入れることが必要です。
イギリスの認知心理学者であるペーター・カスカート・ウェイソン氏が1966年に考案した「ウェイソン選択課題」が有名です。
例えば「1」「4」「赤色」「茶色」と書かれた4枚のカードがあり、「カードの片面が偶数ならば、その裏面は赤い」という仮説を確かめるために、ひっくり返す必要があるカードはどれかという課題があったとします。
「4と赤色」のカードを裏返そうと思ったのであれば、不正解です。正しくは「4と茶色」です。なぜなら、仮説の反例になるのは「偶数が書かれている裏が赤色ではないカード」だけだからです。
つまり、「自分の考えと反証する情報に目を向ける」習慣をつけることが大切です。
こうしたバイアスはなかなか抜けづらいものです。しかし意図的に思考する癖をつけたり、会議のアジェンダに取り入れて行動していくことで、徐々に慣れていくことが可能です。
ぜひ、意識して取り組んでいきましょう。
エンでご支援できること
エンが提供するTalent Viewer(タレントビューアー)は、「タレントパレット(株式会社プラスアルファコンサルティング)」の多機能なシステムと、エンが40年間人材領域で培った課題解決サポートを組み合わせた、タレントマネジメントシステムです。
あらゆる人事データを一元管理し、人事課題の要因分析や仮説検証を行うことで、人的資本経営や戦略人事を支援します。
ご興味がございましたら、ぜひ一度お問い合せくださいませ。