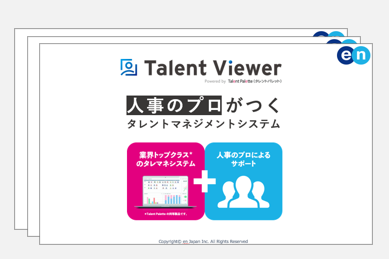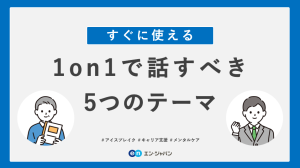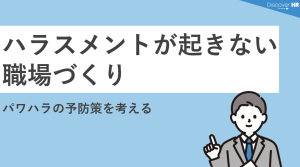エンの教育サービスは何をしているのか?
前回は、エンで行なっている評価領域のサービスについて、サービス責任者の勝又さんをインタビューしました。今回は教育領域についてお話を伺っていきます。

勝又 康仁 氏
エン・ジャパン株式会社 教育評価サービス 責任者
twitter:@katsumata_en
株式会社ビジネスコンサルタントにて、営業・営業マネジメント経験を経てエン・ジャパン株式会社に入社。人材開発および人事評価コンサルタント、グループマネージャーを経て現職。“誰もが自己実現できる社会をつくる”というミッションを掲げ奮闘中。
エンの教育サービスについて、まずは概要を聞かせてください。
エンの教育サービスは大きく2つあります。1つは「eラーニング」で、オンデマンドで講座を視聴できるもの。もう1つは「集合研修」です。これは日時や場所を指定して、そこで受講者が集まって研修を受けます。だいたい半日から、2日間程度の研修が多いです。
直近ではコロナ禍ということもあり、このeラーニングの需要が特に高まりました。リモートが進んだことでeラーニングそもそものニーズが増えたこと、加えて集合研修のオンライン化が急速に広まったことが要因です。我々も、ウェブ会議サービスなどを利用して対応を進めました。
教育サービスについて、力を入れていることはありますか?
教育サービスについて力を入れているポイントは3つです。
- 動機づけ
- プログラム内容
- 効果測定
1. 動機付け
まず、動機づけについてですが、昨今は「学びたいものは何でも自由に学べる時代」と言えます。スマートフォンやパソコンにアクセスすれば各人が知りたいことをすぐ知ることが出来る時代において、まずもって重要になるのは『動機づけ』でしょう。
「コンテンツはある。見る動機はない。」というのが、教育業界の一番の課題です。つまり、今起こっているのは「情報格差」ではなく「学習意欲格差」なのです。
エンでは学習意欲醸成のために【CareerSelectAbility©(キャリアセレクタビリティ)】の考え方を用いています。
これは、【Cereer(キャリア)】【Select(選ぶ)】【Ability(能力)】を組み合わせた造語で、【キャリア自己選択力】といいます。転職や社内異動の際、様々な選択肢の中から自分の望むことを選択できるだけの能力。転じて、時代や事業、環境が変わっても、どこでも活躍できる普遍的な能力のことを意味します。
研修対象者は、まず研修を受講する前にこの【CareerSelectAbility©(キャリアセレクタビリティ)診断】を受け、で自分の強み・弱みを可視化します。自分の仕事の役割やキャリア希望と照らし合わせて「もっとも能力開発したほうがよいと思われる能力」を確定させてから講座の受講をはじめてもらいます。これにより学習の目的を明確にすることができます。
意欲のない研修は効果が落ちますから、動機づけは非常に大切にしています。
昨今はVUCA(ビジネスや市場といった世界におけるさまざまな不安定要素があり、将来予測が難しい世相を指す)といわれていますが、そのVUCA時代にこそ必要なことが【CareerSelectAbility©(キャリアセレクタビリティ)】の考え方だと思います。
エンの「次世代型人事戦略」を読む
https://corp.en-japan.com/success/23561.html
2. プログラム内容
次に、2つ目のポイントは「プログラム内容」です。エンでは抽象的な理論ではなく実務に活かせるプログラムづくりを意識しています。頭が良くなって知的に見えることが目的ではなく、学んだことを如何に現場の問題解決に適応していくかが重要ですから、抽象的な理論はあまり役立たないのです。
そのため講座内容は具体的につくられており、また、隙間時間に学べる工夫を凝らしています。受ける時間がなくて実践に活かせないとなると、本末転倒ですからね。
例えばエンカレッジというeラーニングサービスでは、総講座数は900にのぼりますが、講座を構成しているチャプターだけ見ても学べるように工夫しています。チャプターまで含めて計算すれば、1講座5チャプターだとしても4500のマイクロコンテンツがあることになり、学びたいときに、学びたいことを選び取れる仕組みを構築しています。
3. 効果測定
最後のポイントは「効果測定」です。多くの研修は理解度テストや研修アンケートを用いた結果管理になっていることが多いようです。ただ、冷静に考えてみると、「理解したからなに?」「研修に満足したからなに?」ということになりますよね。理解しているかどうか、研修に満足したかどうかより、大切なのは社員の行動が変わること、現場が変わっていくことです。
だからこそ、エンでは「行動が変わったかどうか」「組織が変わったかどうか」を効果測定の指標とすることを推奨しています。
具体的には、人事評価制度との連動です。
期初にどんな能力を開発していくか目標設定し、目標に定めた能力を開発できる教育プログラムを選択する。受講し、どのように自分の行動を変えていくのか、計画をたてる。計画において定めたアクションプランを実践する。実践して能力の発揮度合いが高めれば、もちろん期末に評価結果もよくなる。
このようなサイクルをつくることで、教育と実践、能力開発後の人事評価と連動させているのです。もちろん、サービスとしてだけでなく、エン内部の教育と評価も、このような形になっているんですよ。
未来の企業における教育はどうなると思いますか?
よりデータ・ドリブンになっていくでしょうね。
キャリアセレクタビリティ診断のことをお伝えしましたが、この診断結果をもとに受講講座のレコメンドを行うこともこの1つでしょう。
診断結果をデータでシステムにインプットしたら、今後は自分の弱みを克服するための適切な講座をレコメンドすることも可能。これは、実際にタレントビューアーを使えばすでに可能ですよね。
学習者1人ひとりに最適な学習内容を提供することで、より効率的、効果的な学習を実現する方法のことをアダプティブラーニングと言いますが、これはBtoCのほうが先行しているといわれています。たとえば、塾とか英語学習などですね。一問一答形式で問題を出題できるとアダプティブ化しやすい。また、受講後の効果測定についても同様です。
ちゃんとデータを管理していけば、研修で学んだことを実践している人は誰か、または、実践度も計測していくことができます。そうすると、誰に教育投資していけばよいかもわかるし、実践度の高いプログラムはどれかもわかります。
能力開発がなされて行動が変われば手段は何でもよい
ちなみに、僕は「別にeラーニングを受講しなくてもよい」と思っています(笑)。それは、目的は受講をすることではなく、行動変容に置くべきだからです。
研修がなくても行動が変わる支援をする、それが究極の目標です。それを実現するためにデータを取り続けていく必要があります。そのほうが、PDCAを回していけますよね。
最後に、今後の教育について、一言お願いします。
教育はアナログ文化にまみれてきた
教育は良くも悪くもアナログ文化が強いと思います。データをとることもしてこなかった。
だからこそ、伸びしろのある分野でもある、と考えています。
エンは
- 研修前の動機づけ
- プログラムのマイクロ化
- 評価との連動による行動変化にフォーカス
- データ・ドリブン化
を軸にこれからも教育サービスをブラッシュアップしていきます。
エンでご支援できること
エンが提供するTalent Viewer(タレントビューアー)は、「タレントパレット(株式会社プラスアルファ・コンサルティング)」の多機能なシステムと、エンが40年間人材領域で培った課題解決サポートが組み合わさった、タレントマネジメントシステムです。
あらゆる人材データを一元化・分析し、人事業務の効率化、経営・人事戦略の意思決定、次世代人材の育成、最適配置、離職防止、採用強化など、人事戦略の精度を飛躍的に高めます。